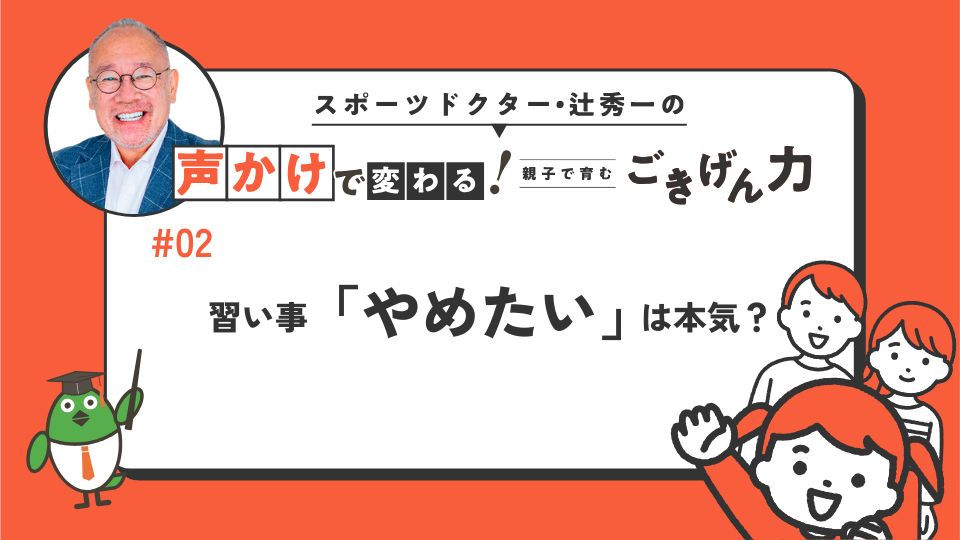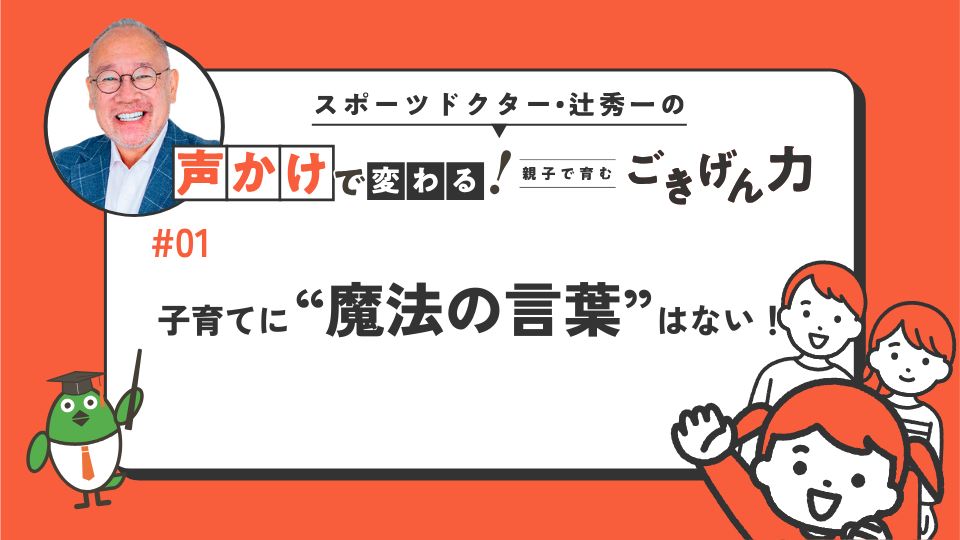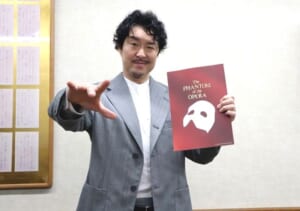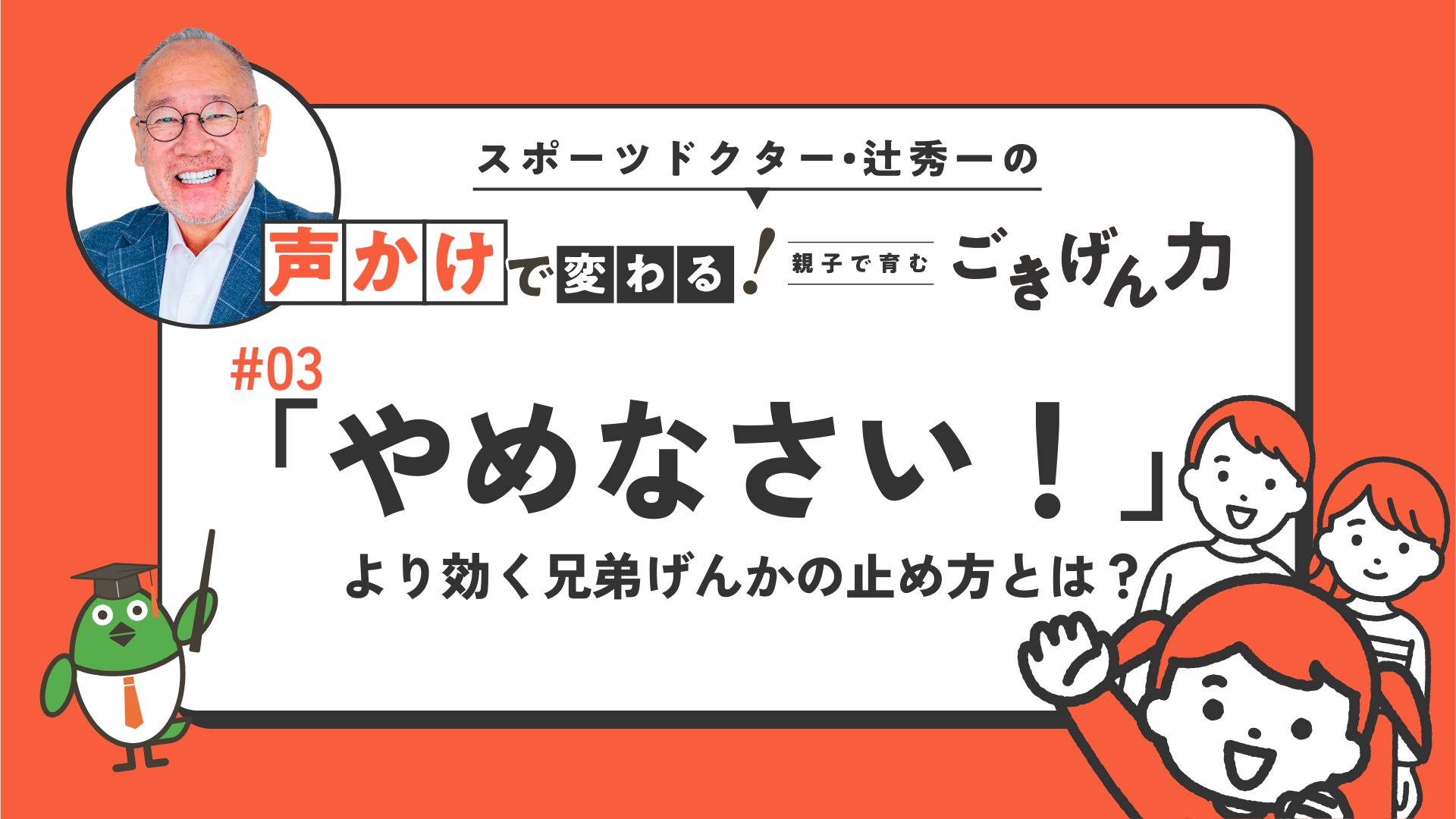ファンファン福岡に集まった福岡の子育て世代の悩みに答える「声かけで変わる!親子で育むごきげん力」。スポーツ界や教育現場でメンタルサポートを行うスポーツドクター・辻秀一先生が、親子のごきげん力を育むためのヒントをお届けします。
今回のテーマは、家庭でよくある「兄弟げんか」。
「またけんか?」「どっちが悪いの!」と叱ったあとに、声を荒げてしまったことに自己嫌悪…。そんな経験をしたことのある方も多いのではないでしょうか。
今回は、兄弟げんかに親はどこまで介入すべきか、そして感情的にならずにどう声をかければいいのかを、辻先生に伺いました。
正しいかどうかを決める必要はない
Q:小学生の兄弟が毎日のように口げんかをします。旅行先でも言い合いが始まり、つい強い口調で「静かにしなさい」「けんかを続けるならゲームの時間減らすよ」と言ってしまいます。どんな叱り方がよいのか悩んでいます。
辻先生 私にも娘が二人いて、姉妹げんかはよくありました。
子どもは意思が未熟なので、育っていく過程で自分の考えを強く主張します。また、自分にとって近い存在ほど遠慮なくぶつかります。だから衝突は自然なことなんです。
大事なのは、どちらが正しいかを決めることではなく、両方の考えと感情を理解してあげること。
「お姉ちゃんの考えも分かるし、それで悲しくなった気持ちも分かる。妹の考えも分かるし、イライラした気持ちも分かる」と双方の感情を理解するようにしましょう。
同意する必要はありません。
「アグリー(同意)ではなくアンダースタンド(理解)」。
そして、叩くなど相手を傷つける行動に対しては「やめなさい」と指示する。
「感情は理解する=支援」、「行動には線を引く=指示」。この両立が大切です。
親がご機嫌でいられるかがカギ

ー叱るとき、つい感情的になってしまいます。
辻先生 子どもに理解を示すには、親に“余裕”が必要です。
でも、兄弟げんかに巻き込まれると親まで不機嫌になり、強い口調になってしまいますよね。
だからこそ「親自身が自分の機嫌をとる練習」が大切です。
子どもはけんかしてもすぐ仲直りできますが、大人は引きずって不機嫌なまま食事をしてしまうこともあります。
まずは「ご機嫌でいることに価値を置く」と決めましょう。
私自身も最初はできませんでしたが、練習を重ねてできるようになりました。
親がセルフマネジメントできれば、余裕を持って子どもに的確な指示と温かい支援ができます。
結局のところ「子どものために何をすればいいか」への答えとしては、「まず自分がご機嫌でいること」からなんです。
親自身の「自分育て」が子育てになる
ー自分の機嫌をとる練習は、どうすればできますか?
辻先生 瞬間的にカッとなることは誰にでもあります。
だからこそ日頃から“自分の感情に気づく練習”が必要です。
「イラッとした」「不安になった」と感じた時、その原因は子どもではなく「自分の思考」にあります。
例えば“片付けてくれるはず”と期待したから怒りが生まれる。
不機嫌をつくっているのは子どもではなく、自分自身なんです。
だから、なぜ不機嫌になったのかを客観視する練習を続ける必要があります。
こうして感情をマネジメントすることが親の仕事でもあります。
そしてそうやってセルフマネジメントできれば、会社でも良いリーダーになれます。
著書にも書いていますが、本当に大切なのは「大人がどうあるか」。
そこに集中すれば自然と的確な声かけができるようになります。もちろん簡単ではなく練習が必要です。
「子どもを育てる前に自分を育てる」こと―これが何より大事なんです。
声かけのヒント
- 「お姉ちゃんの悲しくなった気持ちも分かるし、妹ちゃんのイライラした気持ちも分かるよ」
- 「気持ちは理解するけど、手は出さないでね」

辻 秀一(つじ しゅういち)
スポーツドクター、メンタルコーチ、産業医。株式会社エミネクロス代表取締役。1961年東京都生まれ。北海道大学医学部卒業後、慶應義塾大学スポーツ医学研究センターでスポーツ医学を学ぶ。1999年、QOL向上を目的に株式会社エミネクロスを設立。
独自の「辻メソッド」による非認知スキルのメンタルトレーニングを展開し、オリンピアンやプロアスリート、企業、教育現場まで幅広く支援。Dialogue Sports研究所代表理事も務める。
著書に『個性を輝かせる子育て、つぶす子育て』(フォレスト出版)、『スラムダンク勝利学』(集英社インターナショナル)『自己肯定感ハラスメント』(フォレスト出版)など多数。